Endorphin
脳内の神経伝達物質
 視覚・味覚・聴覚・触覚・嗅覚、いわゆる「五感」を使って脳に刺激を与えると、エンドルフィンは多く放出される。
視覚・味覚・聴覚・触覚・嗅覚、いわゆる「五感」を使って脳に刺激を与えると、エンドルフィンは多く放出される。
エンドルフィン(ENDORPHIN)は、脳内で機能する神経伝達物質のひとつで、「体内で分泌されるモルヒネ」である。食欲、睡眠欲、生存欲、性欲、集団欲などの欲求が満たされると最も分泌されるのがエンドルフィンである。但し、物理的欲求は目的が満たされれば、今度はそれを失う不安に代わる(ノルアドレナリンが抑制として機能するから)。
ドパミン
違法ドラッグであるコカインや覚醒剤(メスカリンなど)は、脳内にドパミンという物質の過剰な放出をおこし、覚醒作用や快の気分を生じさせるものであるが、逆に不安や抑鬱をもたらす(バッドトリップ)をも引き起こしてしまう。ステーブ・ジョブズは過去に様々な薬物常習者であり、コカインはもちろん、大麻やLSDに至っては毎日やっていたと自身の伝記で明かしている。
自分自身が全てを受け入れて完結できるような欲望は、ただ愛するという欲求だ。だれかを愛するというのではなく、「愛する」という「受け入れる心」をただ純粋に高めていくような精神的な欲求は、エンドルフィンの放出をいつまでも持続させるといわれている。これは、純粋欲といわれている。
単純で、重量化しない精神構造は、ミニマリズムと自分の価値観やライフ・スタイルに信念を持つことであると思っている。
一般的に人間に本能行動はほとんど無いかわずかであると見なされている。また社会学、哲学、心理学の一部では本能を「ある種の全ての個体に見られる複雑な行動パターンで、生まれつき持っており、変更がきかない」と定義する。この定義の元では性欲や餓えも変更がきくために、本能とは言えないと主張される。極端な行動主義や環境決定論においてはあらゆる種類の「本能」が否定され、行動はすべて学習の結果として説明される。─wikipediaより引用
From "The Funny Side of Physic" by A. D. Crabtre

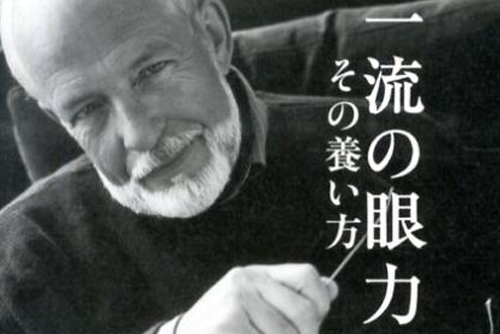 川北義則が日本の男たちに届けたい言葉がここにある。腹を割って男同士で語る本音が炸裂する。女性の方には反感を買うかもしれない。ジェンダー世代の男たちにとっては非常に評価が割れている本であるらしい。
川北義則が日本の男たちに届けたい言葉がここにある。腹を割って男同士で語る本音が炸裂する。女性の方には反感を買うかもしれない。ジェンダー世代の男たちにとっては非常に評価が割れている本であるらしい。 レイモンド・チャンドラーの小説は高校生のときに読んで心酔してしまった記憶がある。あれから暫らく経って、こよなくチャンドラーを愛好している村上春樹が翻訳して2007年3月に大都会の孤独と死、愛と友情を謳いあげた永遠の名作を「完訳版」として鮮やかに蘇らせたのだった。村上春樹も何度も繰り返し読んだらしいが、どうして読み飽きることがなかったのだろう。
レイモンド・チャンドラーの小説は高校生のときに読んで心酔してしまった記憶がある。あれから暫らく経って、こよなくチャンドラーを愛好している村上春樹が翻訳して2007年3月に大都会の孤独と死、愛と友情を謳いあげた永遠の名作を「完訳版」として鮮やかに蘇らせたのだった。村上春樹も何度も繰り返し読んだらしいが、どうして読み飽きることがなかったのだろう。 大沢在昌のハードボイルドを読んだ。大沢在昌の心は漢(おとこ)にあるようだ。だから読んでいるうちにウズウズしてきて力が漲ってくる感覚がある。
大沢在昌のハードボイルドを読んだ。大沢在昌の心は漢(おとこ)にあるようだ。だから読んでいるうちにウズウズしてきて力が漲ってくる感覚がある。